
女の子の健やかな成長を願う、ひな祭り。
雛段飾りをして家族や親戚などが集まって皆でお祝いするイメージが多いですが、実はもともと女の子のための行事ではなかったことをご存知でしょうか。
ひな祭りは、古代中国の上巳の節句で行われていた邪気を払う風習から生まれた伝統行事です。
今回はひな祭りの起源や現在の形になるまでの歴史、上巳の節句や桃の節句について紹介します。
当日にやることや過ごし方、雛人形の役割、ひな祭りにまつわる行事食についても解説しますのでご参考になれば幸いです。
他の年中行事・イベントについては、下記記事でまとめていますので併せてご参考ください。
ひな祭りとは
ひな祭りは、女の子の健やかな成長と幸せを祈る日です。
しかしもともとは、女の子のための行事ではありませんでした。
ひな祭りの起源

ひな祭りは、中国から伝わった「上巳の節句」が由来です。
中国では五節句の1つである上巳の節句がやってくると、川で身を清める習慣がありました。
この厄災を払うための行事が日本へ伝わり、雛遊び(ひいなあそび)と結びついて現在の形ができたとされています。
雛遊びについては別記事で紹介しますが、日本では紙などで作った人形で自分の身体をなでて穢れ(けがれ)を移し、川に流すことで邪気祓いをする行事として伝わっていきました。
人形を流して邪気を払うこの風習が、現在でも一部の地域で残っている「流し雛」のルーツです。
雛遊びについては、下記記事をご参考ください。
-

-
雛人形が現在の形になるまでの由来や役目とは?ひな祭りに飾る理由や時期、並べ方
2025/1/18
五節句の1つ、上巳の節句とは

中国では昔から五節句という行事があり、季節の節目を意味する節には邪気が入りやすいとされていました。
その五節句の1つが上巳の節句で、古代中国で旧暦3月の最初の巳の日のことです。
巳(ヘビ)は脱皮をして生まれ変わることから、上巳には災いや穢れ(けがれ)を払うために水で身体を清めて宴を催す習わしがありました。
川のほとりに集まって災厄を払うこの行事は「上巳の祓い」と呼ばれています。
五節句については、下記記事をご参考ください。
-

-
五節句とは?人日・上巳・端午・七夕・重陽の意味、行事に使われる五色の秘密
2025/1/22
別名で桃の節句とも

上巳の節句にあたる時期は、ちょうど春が訪れて桃の花が咲く頃です。
昔は上巳の節句として3月で最初にくる巳の日を指していましたが、後に3月3日に定められました。
そして江戸幕府によって5つの節句が制定され、3月3日は桃の花が咲く季節でもあることから「桃の節句」とも呼び、現在もその言葉が使われています。
上巳の節句よりも桃の節句のほうが知られるのには、季節を表すための言葉が入っていて覚えやすいからかもしれませんね。
ひな祭りはいつ?

ひな祭りの由来が上巳の節句からくることを先に説明しましたが、結局のところひな祭りはいつなのでしょうか?
現代におけるひな祭りは、基本的に3月3日が当日です。
地域によっては4月3日に行うところもありますが、旧暦の3月3日は現代の新暦で4月3日に該当します。
そのため、昔の人と同じ旧暦で行事を行う地域や家庭では4月3日に行うようです。
実際に4月3日は桃の花が咲く季節でもあるため、桃の節句の名前にふさわしいタイミングといえます。
ひな祭りを行う日として、3月3日と4月3日のどちらかが誤りというわけでは決してありません。
お住まいの地域や家庭に合わせたタイミングにお祝いをするとよいでしょう。
旧暦と新暦については、下記記事をご参考ください。
-
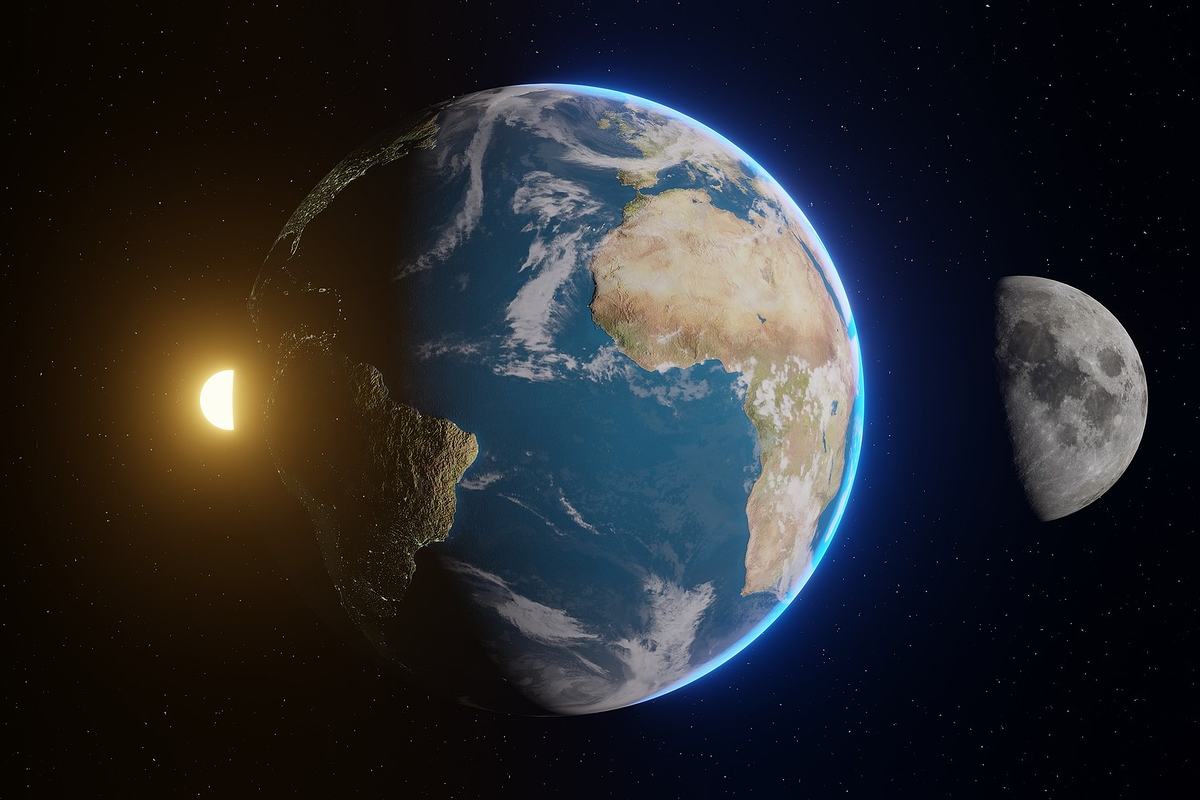
-
暦の定義とは?太陰暦や太陰太陽暦、太陽暦の仕組みや違い、うるう年の役目
2025/12/13
ひな祭りにやること・過ごし方

ひな祭りは、女の子の健やかな成長を祝う日です。
平安時代から続く日本の伝統行事として、当日はどんなことをやるのでしょうか。
雛人形を飾る

ひな祭りといえば、女の子の成長を祝いこれからの幸せを願いながら雛人形を飾る風習があります。
雛人形は上巳の節句に川で身を清める中国の習慣と結びつきがあり、平安時代に女の子たちの間で流行った雛遊びが変化したものです。
現代では、娘を授かった親の子の幸せを想う気持ちや女性を災いから守るといった役割があります。
雛人形の由来については、下記記事を併せてお読みください。
-

-
雛人形が現在の形になるまでの由来や役目とは?ひな祭りに飾る理由や時期、並べ方
2025/1/18
雛あられや菱餅を食べる

雛段飾りの最下段には、雛あられや菱餅などひな祭りにまつわるお菓子を並べるのが一般的です。
詳しくは後述しますが、雛あられや菱餅には四季を表す色で構成されていることから、1年を通して子どもの幸せを祈るという意味が込められています。
行事食を作って食べる

ひな祭りには家族みんなで祝う行事として、両家の両親を自宅に招くなどお祝いの席や会食をもうけてご馳走でもてなすのが習わしとされてきました。
会食の席ではちらし寿司やハマグリのお吸い物、甘酒(白酒)などの定番料理が並びます。
これら行事食にはそれぞれに意味があり、詳しくは後述します。
桃の花を飾る

ひな祭りが桃の節句とも呼ばれるのは、旧暦3月3日が桃の咲く時期と重なるためです。
本来なら桃の花は3月中旬から4月にかけて咲きますが、旧暦の3月3日は現代の新暦で約1ヶ月のずれがあり4月3日頃になるためちょうど咲いている頃になります。
桃の花を飾る理由として中国では桃が厄や邪気を払う縁起のよい植物とされており、日本では古来から桃が魔除けの効果をもつと信じられていたためです。
桃の節句は、家族の健康や安全を願う日としても大切にされてきたといえます。
ひな祭りにまつわる行事食の意味
ひな祭りに食べるものといえば、雛あられやちらし寿司、ハマグリのお吸い物などが挙げられます。
これらをひな祭りに食べるのには、実は理由や意味があるのをご存知でしょうか。
雛あられ(ひなあられ)

雛あられ(ひなあられ)は、江戸時代に「雛の国見せ」という雛人形を外に連れ出していた遊びに、女の子たちがお菓子として持っていったものが始まりです。
雛人形に外の美しい景色を見せてあげるために、雛人形と一緒にお出かけをする時に持っていくお菓子が雛あられだったといわれています。
1粒1粒が桃・緑・黄・白の4色で構成されているのは春夏秋冬の四季を表しており、1年を通して子どもたちの幸せを祈るという意味が込められているのです。
また自然のエネルギーにあやかり、健やかに成長するようにという願いも込められています。
雛あられの味付けは、地域によって異なります。
関東では米を爆発させて作るいわゆるポン菓子を指し砂糖で甘く味付けしたものですが、関西では塩や砂糖醤油で味付けした餅を揚げたものです。
菱餅

菱餅(ひしもち)は、緑・白・桃3色の餅を重ねて菱形に切り重ねたものです。
ひな祭りの起源とされている上巳の節句と共に中国から伝わった風習で、もともとは母子草(ははこぐさ)という草餅でした。
しかし母子をついて餅にするイメージから嫌がられるようになり、日本ではヨモギを使うようになったといわれています。
緑・白・桃の3色で重ねられているのは、緑は草、白は雪、桃は桃の花という風景を表しているとされています。
他に緑は健康や長寿、白は清浄、赤は魔除けという意味も込められているという説もあります。
また色をつけるために桃(赤)にはクチナシ、緑にはヨモギが混ぜられていますが、どちらも邪気を払うと信じられてきた植物です。
そして、菱形の形状は心臓・心を表しています。
ちらし寿司

まず第一に、寿司は「寿を司る」と意味することからおめでたい席で食べることとされています。
ちらし寿司は、もともとは平安時代に現在のお寿司の原型ともいえる「なれ寿司」に、エビや菜の花を乗せて彩りをよくして食べられていたのが由来です。
次第にその習慣が受け継がれていくうちにより華やかで見栄えのするものに変化していき、現在の「ちらし寿司」になりました。
ちらし寿司にのっている具材それぞれにも、おせち料理と同じ意味があります。
| 主な食材 | 意味・願い |
|---|---|
| エビ | 腰が曲がるまで長生きできるように |
| 豆 | 健康でマメに働けるように |
| レンコン | 先が見通せるように |
| ニンジン | 根をはるように |
| 錦糸卵 | 財宝が貯まるように |
ちらし寿司の色にも意味があり、赤や桃は魔除け、白は子孫繁栄、緑は厄除けや健康を表しています。
ハマグリのお吸い物

ハマグリのお吸い物も、ちらし寿司と一緒に食べられる行事食の1つです。
ハマグリには1対2枚の貝殼をもつ「二枚貝」という意味があり、対の貝はぴったりと合うもののそれ以外の2枚の貝が合うことは絶対にないという特徴に由来しています。
つまりハマグリのその特徴は仲のよい夫婦を表すものとされ、一生1人の相手と永遠に連れ添うようにという願いが込められています。
甘酒(白酒)

日本では、古くから厄を祓い長寿を願う意味を込めて白酒を飲む習慣があります。
もともとは中国の儀式として、邪気を祓い不老長寿を与える桃の花を酒に入れた桃花酒(とうかしゅ)を飲んでいたのが由来です。
この桃花酒に、桃の花や香りが引き立つ酒として白酒を飲む風習になっていきました。
しかし白酒には約9%のアルコール分を含むため、未成年の子どもは飲めません。
そこで子どもでも飲めるように、ノンアルコールの甘酒を用意されたわけです。
参考として甘酒は2種類あり、酒を搾った後に残る酒粕から作られた甘酒にはわずかにアルコールが含まれています。
米麹から作られた甘酒はアルコールを一切含んでいないため、購入の際には注意してください。
桜餅

桜餅もひな祭りにいただく和菓子として広く知られており、和菓子店やスーパーなどの店頭でも並びます。
ひな祭りに桜餅を食べる理由は諸説ありますが、5月5日のこどもの日(端午の節句)には柏餅を食べる習慣があることから、それと対になるようにひな祭りには桜の葉で餅を包む桜餅で食べられるようになったともいわれています。
桃と緑の色合いで春らしさを感じて、まさに桃の節句にふさわしい行事食です。
江戸時代から作られていたとされる桜餅ですが、実は関東風と関西風という2つの種類があるのをご存知でしょうか。
関東風の桜餅:長命寺

関東風(江戸風)の桜餅は、「長命寺(ちょうめいじ)」といい、小麦粉で作った生地をふたつ折りにして餡をはさんだものです。
関西風の桜餅は:道明寺

関西風(上方風)の桜餅は、「道明寺(どうみょうじ)」と呼び、道明寺粉と呼ばれるもち米を粗く挽いて作られているため、つぶつぶとした食感があります。
筆者が以前に勤めていた職場で毎年ひな祭りの日がやってくると、同じ部署のおじさまが女子全員に桜餅を差し入れしてくれたものです。
奥様の手作りで粗いつぶつぶとした桜餅だったため、今さらながら関西風の桜餅だったことに気づきました。
苦手でいつも外していた桜の葉も美味しく、塩味のきいた甘さ抑えめの優しい桜餅だったのを昨日のことのように思い出します。
厄を祓い健康を祈るひな祭りまとめ

桃の節句でもある3月3日に行われる、ひな祭り。
現代におけるひな祭りは、間違いなく日本独自の伝統行事です。
女の子たちの雛遊びと上巳の節句が結びついて発展していったものです。
現代では節句祭りの1つとして、雛人形や桃の花を飾ったり雛あられや菱餅などを食べたりしながら女の子らしい彩りのある空間を演出するのが慣習となっています。
そして雛人形が子ども孫へと次の世代へ受け継がれていくという風習は、平安時代からの日本の伝統文化としていつまでも守り続けていきたいものですね。
以下の記事では、雛人形が現在の形になるまでの由来、ひな祭りに飾る目的や役割について紹介しています。
雛人形の種類やそれぞれの意味、飾る時期や並べ方・注意点についても解説していますので併せてお読みください。
-

-
雛人形が現在の形になるまでの由来や役目とは?ひな祭りに飾る理由や時期、並べ方
2025/1/18










