
暦の上では秋だけど厳しい暑さの残る時期に送る残暑見舞い。
夏の疲れが出る頃に故郷の友人や親族、お世話になった人たちがどうしているか気になることも多いでしょう。
そんな時に送る残暑見舞いは、いつからいつまでに送ったらいいのか。
相手との関係に応じてどういう書き方や送り方をしたらいいのか。
今回は残暑見舞いの意味や送るのに適した時期、挨拶状の書き方を文例付きで解説します。
最後には夏の疲れに喜ばれる人気のギフトを紹介していますので、お中元や暑中見舞いを送る機会を逃した場合の贈り物としてご参考になれば幸いです。
\最新型番から生産終了型番まで豊富な品揃え/
残暑見舞いとは

残暑見舞いは、遠方に住んでいてあまり会えない友人や恩師、いつもお世話になっている人へ送る「晩夏の挨拶状」です。
夏の厳しい暑さがまだ残る時期に、相手の健康を気遣う気持ちを込めて送ります。
ハガキでの短いお便りですが、メールよりも手書きの方が温もりがあり形あるものとして丁寧な印象を与えられるのが魅力な点です。
また自身の近況報告も兼ねているため、お互いの心を通わせるひとつの手段ともいえます。
残暑見舞いは暑中見舞いと同じく暑さを気遣う挨拶状ですが、大きな違いは送る時期です。
残暑見舞いができた起源や現在の形については、暑中見舞いと同じですので下記記事をご参考ください。
残暑見舞いを送る時期

残暑というのは、夏本番を過ぎてもなお残る暑さという意味です。
残暑見舞いを送る時期は、その前に送る暑中見舞いが二十四節気の立秋前日までに送るとされているため、立秋にあたる8月7日頃から8月末までに送ります。
| 立秋 | 暦の上で秋へ移り変わる8月7日頃 |
| 処暑 | 厳しい暑さの峠を越した9月6日頃 |
ただし近年は暑さが9月まで続き秋の訪れが遅い年や地域もあるため、遅くても処暑にあたる9月6日頃までに送ることができます。
二十四節気については、下記記事をご参考ください。
立秋はいつ?

前述の通り、残暑見舞いは二十四節気の立秋にあたる8月7日頃から8月末までに送るのが基本です。
9月になっても暑さが続く年や地域もあることから、遅くても処暑にあたる9月6日頃までに送ることになります。
ただし二十四節気の立秋や処暑は、年ごとに日にちが異なります。
今後5年間の立秋と処暑にあたる時期は、以下の通りです。
| 年 | 立秋 | 処暑(最終日) |
|---|---|---|
| 2025年 | 8月7日 | 8月23日(9月6日) |
| 2026年 | 8月7日 | 8月23日(9月6日) |
| 2027年 | 8月8日 | 8月23日(9月7日) |
| 2028年 | 8月7日 | 8月22日(9月6日) |
| 2029年 | 8月7日 | 8月23日(9月6日) |
ただし残暑見舞いを送る時期があまり遅いと送る相手の住んでいる地域や気候によっては、朝晩の涼しさに初秋の気配が感じられ季節感を損なう場合もあるため気をつけてください。
個人的には、一般的な8月末までに出せば問題ないと考えます。
お中元や暑中見舞いとの扱い
残暑見舞いは、暦の上では秋を迎えても実際は厳しい暑さがまだ続いている時期に出す挨拶状です。
そのため、お盆休みにゆっくり書きたい人に向いています。
またお中元を贈る時期を過ぎてしまった場合や暑中見舞いを出す時期が遅くなってしまった場合は、残暑見舞いとして送ることが可能です。
なお暑中見舞いをすでに送った場合は、残暑見舞いを送る必要はありません。
ちなみに暑中見舞いは、小暑にあたる7月7日頃から立秋にあたる8月7日頃の前日までの1年で最も暑い期間に送ります。
例えば暑中見舞いへの返信を送る際には、小暑を過ぎていれば残暑見舞いとして出すのが望ましいです。
暑中見舞いについては、下記記事をご参考ください。
残暑見舞いハガキの書き方
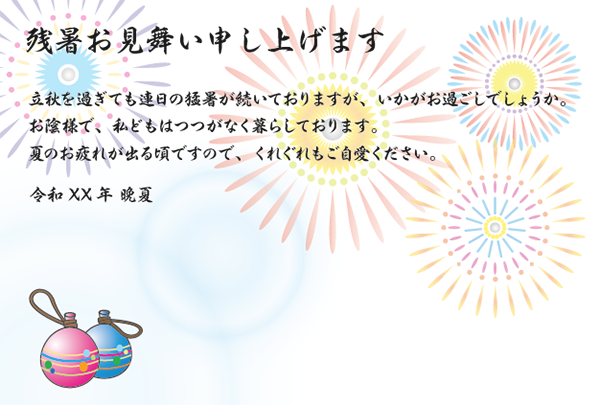
残暑見舞いのハガキは、以下5つの構成で書くのが基本です。
- (1)お見舞いの挨拶
- (2)時候の挨拶
- (3)自身の近況報告
- (4)結びの挨拶
- (5)日付
(1)お見舞いの挨拶
残暑見舞いの書き出しは、「残暑お見舞い申し上げます」となります。
年賀状と同じで「こんにちは」「さようなら」などの頭語・結語は使いません。
また、一般の手紙やビジネス文書に用いられる「拝啓」「敬具」も不要です。
お見舞いの挨拶文は、本文より大きめに書くことで見栄えをよくしましょう。
句点の「。」も要りません。
(2)時候の挨拶
時候の挨拶は、残暑見舞いを送るタイミングに合わせた季節感を表す文章です。
土地や気候など、送る相手の住んでいる地域に適した文章を選びます。
相手が置かれている状況を踏まえた上で相手の安否を尋ねる文章を続け、お世話になったことがあれば感謝のひと言を添えます。
(例)
立秋とは名ばかりの厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか
残暑見舞いで時候の挨拶をする際は、相手の立場に注意しましょう。
離れた土地に住んでいる人に送る場合は、同じ夏でも気候が同じとは限りません。
相手が住んでいる地域や気候に合わせて表現を選ぶと、相手を思いやる気持ちがより伝わります。
(3)自身の近況報告
次に自分や家族の近況を書くと、相手に喜ばれるとともに安心されます。
自身の近況報告は相手との関係に合わせて書くことが重要で、具体的な内容にすることも大切ですが相手が目上の場合は当たり障りのない文章がおすすめです。
(例)
お陰様で、私どもはつつがなく暮らしております。
(4)結びの挨拶
残暑見舞いにおける結びの挨拶とは、相手を気遣う言葉を指します。
一番伝えたいこと、相手への気遣いや感謝を述べて締めくくりたいものです。
(例)
夏の疲れが出る時期ですので、くれぐれもご自愛ください
(5)日付
残暑見舞いの最後に用いる日付は、夏の終わりが近づいても暑さがまだ残る時期という意味として「晩夏」「立秋」を使います。
(例)
令和○○年 晩夏
暑中見舞いと同じく残暑見舞いでは、正確な日付は書きません。
年数の下に、夏の残る季節を表す「晩夏」と書くのが一般的です。
他に「令和○○年 立秋」「令和○○年 八月」などがありますが、縦書きの場合は年号を漢数字で書くという決まりがあるため注意しましょう。
あらかじめデザインされた市販の残暑見舞いハガキや手作りで印刷したハガキを使用する場合には、手書きで一言添えるのもおすすめです。
手書きが1文でも添えられていると、受け取った相手も好印象をもちます。
残暑見舞いを送る参考文例

残暑見舞いの文例を相手別・シーン別に紹介しますので参考にしてください。
友人や親族などに送る場合(一般向け)
友人や親族などに送る場合の一般的な参考文例です。
残暑お見舞い申し上げます
立秋を過ぎても連日の猛暑が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか
おかげさまで、私どもは相変わらず元気に過ごしております
夏の疲れが出る頃ですので、くれぐれもご自愛ください
令和○○年 立秋
上司や社内関係者に送る場合(仕事向け)
上司や職場でお世話になっている目上の人などに送る場合の参考文例です。
残暑お見舞い申し上げます
日頃は何かとお世話になり、誠にありがとうございます
夏の休暇でご配慮いただき、おかげで実家に帰省することができました
今後も一層、業務に励んでまいります
もう少し暑さが続くようですので、ご自愛のほどお祈り申し上げます
令和○○年 晩夏
会社関係者や取引先に送る場合(ビジネス向け)
個人事業主やフリーランスなど起業されている人が、会社関係者や取引先に送る場合の参考文例です。
残暑お伺い申し上げます
貴社におかれましては益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます
まだまだ厳しい暑さが続いておりますので、ご健康にご留意されますようお願いいたします
貴社のますますのご発展をお祈り申し上げます
令和○○年 立秋
お中元の代わりに送る場合
お中元を贈る時期を逃してしまった際、贈答品より早くに送る残暑見舞いの参考文例です。
残暑お見舞い申し上げます
平素より何かとお世話になりまして、心より御礼申し上げます
つきましては、本日、心ばかりの品を別送させていただきました
ご笑納いただけましたら幸いに存じます
今後とも何とぞご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます
本来ならばご挨拶に伺うべきところ、失礼をお許しください
残暑厳しき折、くれぐれもお気をつけくださいますようお祈り申し上げます
令和○○年 晩夏
贈答品のお礼として送る場合
お中元や暑中見舞いの贈答品をいただいたお返しとして、贈答品とは別にお礼の挨拶として送る残暑見舞いの参考文例です。
残暑お見舞い申し上げます
○○(相手の氏名)様には日頃なにかとご配慮を賜り、ありがとうございます
さて、先日はお心のこもったお中元の品をお送りいただき誠にありがとうございます
何よりの好物、ありがたく拝受いたしました
残暑厳しき折から、ご自愛のほどお祈りいたします
取り急ぎ、残暑お見舞いかたがた、お礼のご挨拶とさせていただきます
なお、別送の品は軽少ながら感謝のしるしでございます
お納めいただければ幸いに存じます
令和○○年 晩夏
暑中・残暑見舞いを受け取ったら
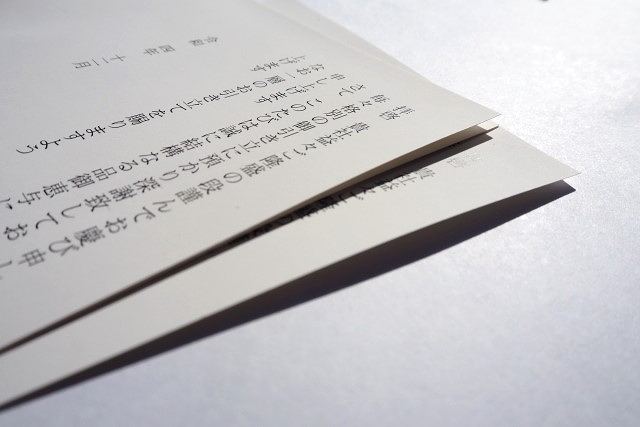
暑中見舞いや残暑見舞いを受け取ったら、返事をするのがマナーです。
ただし暑中・残暑見舞いというのは、基本的に目下の人が目上の人に対して送るものです。
そのため、お礼として出すことはほとんどありません。
もし目上の人からお中元や暑中見舞いを受け取った時は、返事としてではなく残暑見舞いとして出す、あるいは普通のお礼状としてお礼の言葉を添えて出すことになります。
メールでもらったらメールでの返信で問題ありませんが、手書きのハガキや封書でもらった場合は礼儀として同じようにハガキや封書で返事を郵送するのが望ましいです。
暑中・残暑見舞いのお礼を返す場合
暑中・残暑見舞いを受け取ったお礼の挨拶状を、残暑見舞いとして送る場合の文例は以下を参考にしてください。
残暑お見舞い申し上げます
このたびはご丁寧に残暑見舞いをいただき、御礼申し上げます
厳しい厚さが続いておりますが、皆様におかれましてはご健在のご様子、何よりと存じます
私たち家族も休暇をいただき、のんびりと過ごしております
残暑が残っておりますが、なお一層の自愛の程お祈り申し上げます
令和〇〇年 晩夏
残暑見舞いの贈答品・ギフト
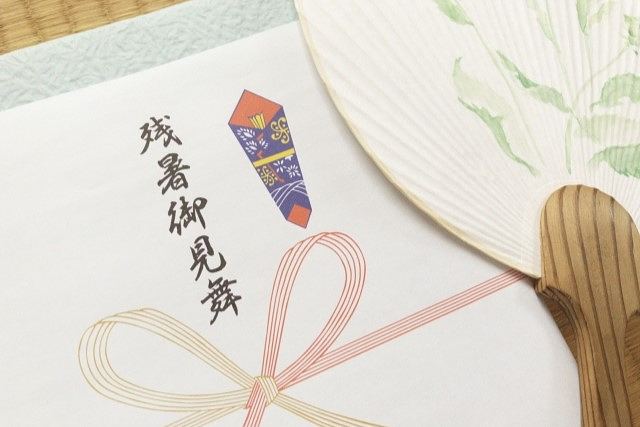
残暑見舞いは、一般的に相手の健康を気遣うために送る季節の挨拶状です。
しかしもともとはお盆に先祖に供え物をしていた流れで、遠方で会えない人やお世話になった人への健康を気遣う気持ちを伝えるために贈答品を送る習慣は今も残っています。
とくにお中元の時期に贈答品を贈れなかった、あるいは暑中見舞いとして贈るタイミングを逃した時には残暑見舞いとして贈ることができます。
贈答品を贈る相場金額
残暑見舞い(残暑お伺い)の予算は、送る相手に負担のない範囲で3000円~5000円が一般的です。
とくにお世話になっている人や取引先には、少し高めの5000円~10000円の予算で考えてもよいです。
付き合いや関係の度合い、相手の年代によって贈答品の金額に違いがありますが、お互いに負担にならない程度にすることが重要です。
贈答品の贈り方
残暑見舞いの贈答品にはのし紙(掛紙)をつけ、表書きは立秋を過ぎてから贈るため「残暑御見舞」「残暑お伺い」となります。
夏の疲れに嬉しい人気のギフト3選
贈る相手に夏の疲れを癒してもらうために、残暑見舞いの贈答品としてふさわしい人気のギフトを紹介します。
フルーツ
夏の暑さを乗り切るギフトとして人気が高い食品といえば旬のフルーツです。
メロンや桃、マンゴーなどが挙げられますが、食べるタイミングが難しいこともあるためゼリーや水羊羹といった涼しげなフルーツの和洋菓子なら日持ちして保存もしやすいでしょう。
また、フルーツの缶ジュースも手軽に飲みやすいのでおすすめです。
和菓子・洋菓子
和菓子や洋菓子は、比較的どこでも買いやすくて無難だと思われがちです。
しかし普段ではあまり購入したり食べたりする機会のない高級菓子や、なかなか手に入らないような人気スイーツはより喜ばれるでしょう。
\季節限定のスイーツに注目!/
ハム
ハムは保存期間も比較的長く、手軽に食べられる点では人気といえます。
種類も豊富で高級感もあるため、普段とは違う贅沢が味わえるのもよいでしょう。
切るだけで食べられるハムは、お弁当のおかずや晩酌のおつまみとしても喜ばれること間違いありません。
肉や魚といったスタミナのつく生ものは相手の事情やタイミング、冷凍・冷蔵の保存期間などに気をつければ、滅多に食べる機会のない希少品や最高ランク品はより喜ばれるでしょう。
夏疲れに相手を気遣う残暑見舞いまとめ
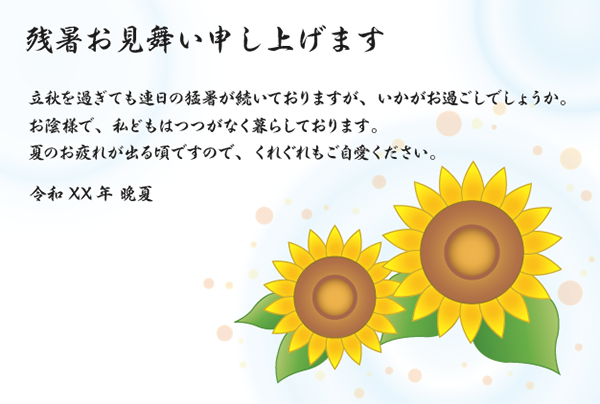
晩夏の挨拶状ともいわれる残暑見舞い。
暑中見舞いや残暑見舞いは、必ず出さなければいけないものではありません。
しかし日頃お世話になっている人や普段会う機会のない人の体調を気遣いながら、感謝の気持ちを伝えたいという想いのもとに送るものです。
過去も現在もお世話になっている取引先、遠方でなかなか会えない故郷の友人や恩師など。
相手のことを思い浮かべながらかしこまらず、あなた自身が相手の体調を思いやりながら素直な気持ちで書いた文章こそ、受け取った人には喜んでいただけるでしょう。
電話やメールなどで気軽にやりとりができる現代では、ハガキや手紙を書いたり送ったりする人は少なくなりました。
たった1枚のハガキですが、やはり形ある季節の挨拶状は年賀状と同じく相手にとって喜ばしいものです。
手書きで一筆添えるだけでも温もりがあり、相手への思いやりもより伝わりやすくなります。
デジタル化が進む中であえてアナログでの通信手段でやりとりし、古くから伝わってきた習慣や夏の風情を届けたいものですね。
以下の記事では、暑さが真っ盛りの時期に相手の体調を気遣う真夏の挨拶状ともいわれる暑中見舞いについて紹介していますので併せてお読みください。






