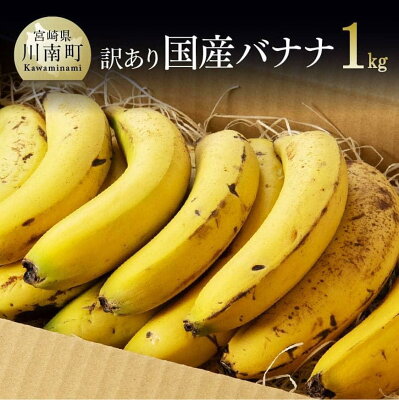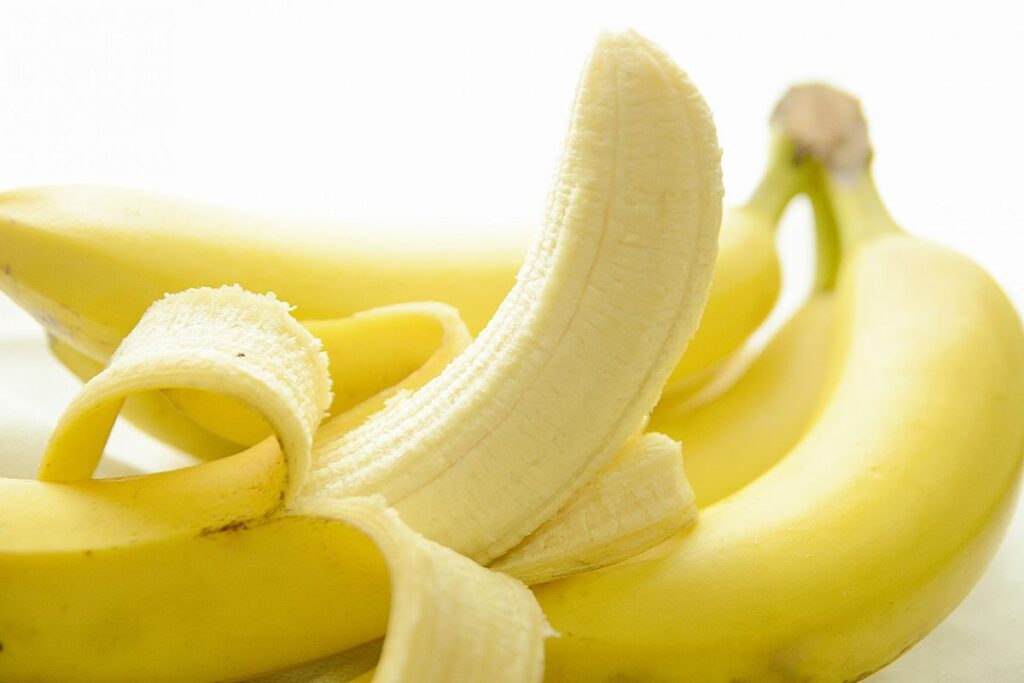
手で皮をむくだけで手軽に食べられるヘルシーな食品、バナナ。
あなたは、バナナに含まれる主な栄養素やそれぞれの作用、効果的な食べ方をご存知でしょうか。
多くの栄養素をバランスよく含むバナナは、健康面や美容面での効果が多く注目されています。
また、1房で300円前後と手軽な値段で、調理道具も要らず生でも食べられるため、コストパフォーマンスも抜群で、普段の食生活で上手に取り入れたい食品です。
今回は、バナナの栄養成分とそれぞれの作用、摂取することで得られるメリットやデメリットを踏まえた上で、効果的な食べ方・注意点も紹介します。
バナナの基本情報
まずは、バナナについて押さえておきたい基本的な情報を解説します。
バナナの種類と流通
バナナといえば、私たちがすぐに思い浮かべるのは、月のように湾曲した円筒形の黄色い果物で、果物の中でも一番手軽で、皮をむけばそのまま生で食べられることでよく知られています。
また、調理に使うとしても、スムージーやバナナケーキなどといった、スイーツの材料として一緒に混ぜ込むというのがほとんどでしょう。
実は、バナナを世界でみると、300種類以上の品種があるといわれています。
日本では一般的に、生食用バナナしかスーパーなどで見る機会はありませんが、世界ではバナナを主食とする国や地域もあり、甘みの少ない調理用バナナもあります。
生食用バナナは、果肉が柔らかく熟したものをそのまま生で食べられるのが特徴です。

調理用バナナは、果皮が緑色のものが多く果肉が硬いため、皮をむいて焼くか煮込むかなどして調理します。
また、乾燥させた果実を、デンプンのような乾燥粉末にすることもあります。
日本では、あまり見かけない調理用バナナですが、世界の国々では辛い料理や甘い料理にも使われ、特にカレーの具材として使われることが多いです。
レストランなどでバナナ入りのカレーを見たことがある人は、甘みを抑えながら食感を残すために調理用バナナを使っています。
ただし、子供向けの甘いカレーは、食感を残さず煮込んで溶かすために、柔らかい生食用バナナを使っていることもあるでしょう。

バナナの生産地と輸入量
バナナの生産地といえば、まずフィリピン産が浮かぶと思いますが、日本では沖縄などの温暖な地域で栽培されています。
バナナの国別輸入量を農林水産省サイトで確認すると、総輸入量は約104万5000トンで、輸入国ランキングの1位がフィリピン、2位がエクアドル、3位はメキシコです。
1位:フィリピン(約83万7000トン、約80%)
2位:エクアドル(約11万9000トン、約11%)
3位:メキシコ(約5万4000トン、約5%)
資料:農林水産省サイト(2019年財務省貿易統計)
筆者が調査した時点では、出典のページが閲覧できていましたが、その後該当ページが消えていたため、果物情報サイト「果物ナビ」をご参照ください。
農林水産省サイトで掲載されているデータと同じFAOSTATのシステムを利用されているため、わかりやすいです。
ちなみに、バナナの生産量ではインドが世界で1位ですが、日本へは輸入されていません。
1位:インド(3,306万2000トン、26.45%)
2位:中国(1,172万4200トン、9.38 %)
3位:インドネシア(874万1147トン、6.99%)
出典:果物ナビ(FAOSTAT・2021年)

バナナの主な栄養成分と作用・効能
バナナは、私たちが想像できないほど、栄養バランスが優れた食物です。
私たちの体に必要な栄養成分を豊富に含んでおり、数ある中から主に期待できる作用や効果を説明します。
バナナの栄養成分表
バナナの可食部100gあたり(目安は1本)の栄養成分表は、以下の通りです。
エネルギー:93kcal
水分:75.4g
タンパク質:1.1g
脂質:0.2g
炭水化物:22.5g
ナトリウム:Tr
カリウム:360mg
マグネシウム:32mg
カルシウム:6mg
リン:27mg
鉄:0.3mg
亜鉛:0.2mg
銅:0.09mg
マンガン:0.26mg
ビタミンA:5μg(レチノール活性当量)
ビタミンB1:0.05mg
ビタミンB2:0.04mg
ナイアシン:0.7mg
ビタミンB6:0.38mg
ビタミンC:16mg
ビタミンE:0.5mg(αトコフェロール)
葉酸:26μg
パントテン酸:0.44mg
食物繊維総量:1.1g
(水溶性食物繊維:0.1g)
(不溶性食物繊維:1.0g)
※Tr=0ではないが微量
出典:日本食品標準成分表2020年版(第8訂)
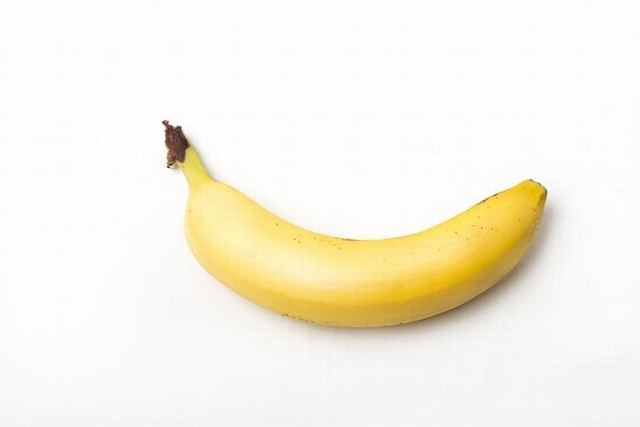
食物繊維
食物繊維は、食後のコレステロールを吸収したり、血糖値の急激な上昇を抑えたりする作用があります。
食物繊維が豊富なバナナは、おなかの調子を整えて便秘解消にもなります。
カリウム
カリウムは、ナトリウムを体外へ排出し、筋肉の収縮や血圧の上昇を防ぎます。
バナナに含まれるカリウムは、体内の塩分を排出し、むくみを解消する作用が期待できます。
マグネシウム
マグネシウムは、人の身体に必要なミネラルの一種で骨を形成するため、骨粗しょう症などを予防する作用があります。
ポリフェノール
ポリフェノールは、強い抗酸化作用があるため動脈硬化や花粉症などを抑える作用があります。
ビタミンB群
ビタミンB群は、エネルギー代謝を助け、粘膜を再生したり免疫機能を維持したりする作用があり、貧血や疲労感を軽減する効果もあります。
ナイアシン
酵素をサポートする補酵素として、タンパク質や脂質、糖質のエネルギー代謝をスムーズにしています。
その他
バナナは、他にも必須アミノ酸のメチオニンやリジンが含まれ、ビタミンB6やビタミンC・ナイアシン・鉄に働きかけることで、脂肪燃焼を促進するカルニチンという成分を合成します。
バナナの摂取効果・メリット
上記で、バナナに含まれる主な栄養成分を理解できたところで、次は日常生活における具体的な効能を説明します。
栄養バランスで免疫力を高める
人の身体は、外から侵入しようとするウィルスや、体内に潜む細菌・がんなどを異物として認識し、無害な状態にしようとする抵抗力(免疫力)を生まれながらにもっています。
免疫力を正常に働かせるためには、適度な運動や睡眠などとともに栄養バランスのとれた食事が必要です。
皮をむくだけで手軽に食べられるバナナは、身体に必要な栄養素を豊富に含んでおり、日々のエネルギー補給に優れた果物です。
バナナは、免疫細胞と呼ばれる血液中にある白血球の働きを促す効果が期待されていると近年の研究で発表されています。
さまざまな食品の中でもバナナが、白血球を活性化させる力が強いことが確認されており、黄色いバナナよりも成熟してシュガースポットが出てきたバナナで高まるといわれています。
シュガースポットとは
シュガースポットは、バナナを数日置いておくことで皮に現れる茶色や黒の斑点です。
スイートスポットとも呼ばれており、バナナが熟して完熟となっている証拠なので、皮が黒くなっている箇所の果肉は、糖分が上がり甘くなっています。
胃腸の粘膜を保護するリン脂質が含まれており、胃腸の荒れや胃潰瘍を防いでくれることも特徴です。

消化酵素が消化吸収を助ける
果肉が柔らかく食べやすいバナナは、消化吸収がよい食品として知られています。
中でもバナナに含まれるアミラーゼという消化酵素が、消化器官での吸収を素早くサポートします。
アミラーゼは、米や小麦はじめバナナにも含まれる炭水化物を消化するために必要な酵素です。
エネルギー供給源である炭水化物を、消化吸収しやすい麦芽糖や腸内環境を改善するオリゴ糖などに分解します。
アミラーゼには食品に含まれているもの以外に、人の体内から消化液として分泌されるものがありますが、加齢とともに体の消化機能は低下します。
アミラーゼを含む食品は、胃腸に負担をかけずに消化吸収できるため、幅広い世代の方におすすめです。
食物繊維などで腸内環境を整える
便秘の予防や改善に欠かせないのが、ほとんどの人がよく知る食物繊維です。
食物繊維は、水溶性と不溶性に分別されますが、バナナはこの両方をバランスよく含んでいます。
栄養成分表に記載されている食物繊維は、この2つの総量となっています。
水溶性食物繊維は、水に溶けるため、便を柔らかくしたり便の滑りをよくしたりして便通を促します。
余分な脂質を吸着して便と一緒に排出したり、糖質の吸収をゆるやかにする働きもあります。
不溶性食物繊維は、水に溶けないため、大腸の水分を吸収して便のカサを増やしたり、大腸に刺激を与えて便の排出を助けたりします。
水溶性と不溶性のどちらも、大腸内で発酵・分解されることで、ビフィズス菌などを増やし、腸内環境を整えてくれるのす。
ちなみにバナナは、可食部分100g当たりで水溶性食物繊維が0.1g、不溶性食物繊維が1.0g含まれています。
また、バナナは、フラクトオリゴ糖を含む特徴もあり、他の糖質と比べて消化されにくいことから、水溶性食物繊維がそのまま大腸まで届き、善玉菌のエサとなって善玉菌の増殖を促し、健康な腸の働きを支えます。

活性酸素を抑えてバランスを保つ
いつまでも若々しく元気でいたいとは、誰もが抱える共通の思いでしょう。
老化の要因のひとつとして近年注目されているのが、体内の過剰な活性酸素の働きによる体の酸化です。
活性酸素は、本来であれば体内に侵入してきたウィルスや細菌から身体を守るためにつくられる成分ですが、必要以上につくり出されると体内の正常な細胞までも攻撃してしまいます。
活性酸素を抑えるために大切なのは、抗酸化作用のある食品を適切に摂ることです。
バナナは、抗酸化物質としてよく知られるポリフェノール類をはじめ、ビタミンAやビタミンC、ビタミンE、βカロテン、βクリプトキサンチン、ケルセチン、リコペンなどを含んでいます。
ビタミンがエネルギー代謝を助ける
個々の体質にもよりますが、太りやすい、なかなか体重が減らない原因は、脂肪の燃焼不足によることもあります。
食品に含まれるタンパク質を骨や筋肉に変えたり、糖質や脂質をエネルギーに変えるために重要な役割を担うのがビタミンB群です。
ビタミンB群が不足していると、食事で体内に摂り入れた栄養素が、身体の成分やエネルギーとして消費されないまま、体脂肪として蓄積されやすくなります。
バナナは、ビタミンB1、B2、ナイアシン(B3)、B6、葉酸などを含み、不足しがちなビタミンB群を手軽に摂取できます。
さらに、必須アミノ酸のメチオニンやリジンが、ビタミンB6やC、ナイアシンなどと共に働くことにより、脂肪燃焼を促進するカルニチンを合成します。
高血圧のリスクを抑制する
日本人に多いとされる高血圧は、慢性的に血圧が高く、血管に負担をかけている状態です。
これを放置しておくと、動脈硬化や脳卒中、心疾患などのリスクになり、予防・改善のために食生活の見直しは欠かせません。
血圧を上げる大きな要因となるのが、塩分(塩化ナトリウム)の摂りすぎですが、バナナは果物の中でも、カリウムやマグネシウムを多く含むため、体内の余分なナトリウムを体外へ排出し、血圧の上昇を抑えます。
また、ビタミンやミネラルは血行促進への改善や血圧を正常化させる働きがあります。
基本的には、食塩摂取量を1日6g未満に抑えることが重要ですが、バナナを食べることで塩分の排出を促し、血圧が上がりすぎるのを抑えるのがスムーズでしょう。

バナナを食べる際の注意点・デメリット
では逆に、バナナを食べる際に注意すべきことやデメリットはないのでしょうか。
中性脂肪が増加しやすくなる
人は、果糖を過剰に摂取すると、中性脂肪が増加する恐れがあります。
食物繊維やビタミンなどが多く健康に最適なバナナですが、食べすぎはよくないため適度に摂取することを心がけましょう。
バナナを食べすぎると、カロリーの摂り過ぎや中性脂肪の増加につながります。
食物繊維やカリウムなどをたっぷり摂取できるバナナは、一見するとヘルシーに見えますが、糖質も比較的多く含んでおり意外とカロリーが高いです。
必要以上に摂取し続けると、体脂肪として蓄積され肥満の原因にもなります。
また厚生労働省や農林水産省によると、1日における果物の摂取量として約200gが推奨されています。
そのため、バナナは1日1本程度を目安に摂るとよいでしょう。

ガスが溜まり胃に負担がかかる
また、バナナには食物繊維と同じような働きをするレジスタントスターチという成分が含まれています。
レジスタントスターチとは、難消化性デンプンのことで、消化されずに腸まで届き、便のかさを増やして便通をよくする不溶性食物繊維と、善玉菌のエサとなって腸内環境をよくする水溶性食物繊維の両方の役割を果たす腸活成分です。
ただし、レジスタントスターチを摂り過ぎると、お腹にガスが溜まったり、膨満感を感じたりすることがあります。
筆者は、バナナを毎朝1本食べるのですが、普通サイズのバナナが売り切れていた時に、半分ほどの小さなバナナを2パックを買い、1日2本を食べたことがあります。
すると、ガスが溜まったような不快感とともに、胃に負担がかかり調子が悪くなったため、以降は1日に1本と決めています。

バナナの効果的な食べ方
上記で取り上げた注意点やデメリットを踏まえて、バナナの効能やメリットを活かして効果的に摂るにはどうしたらいいのでしょうか。
朝バナナで血圧や腸内環境を整える
バナナには、おなかの調子を整える食物繊維やオリゴ糖、マグネシウムなどが多く含まれています。
食物繊維は、オリゴ糖と一緒に腸内細菌の働きを助け、腸内環境を整えてくれます。
また、マグネシウムは腸の動きを活発にし、便通を促す働きがあります。
朝食代わりにバナナを摂ることで、おなかも頭もすっきりして1日を快適に過ごしましょう。
さらに、朝は1日のうちで、最も血圧が上がりやすい時間帯です。
高血圧の人は、朝食にバナナを取り入れることで、バナナなどの果物に含まれるカリウムがナトリウムを排出し、血圧を下げる効果があります。

運動前のエネルギー補給に
人が運動する時には、エネルギーの源になる糖質やアミノ酸を補充することが欠かせません。
空腹時に、エネルギーが足りない状態で運動を続けると、体内のタンパク質がエネルギー源として使われるようになり、その結果、途中で運動量やパフォーマンスが落ちてしまいます。
そのため、運動前はバナナのように消化吸収がよく、糖分を含んだものを軽く食べておくとよいでしょう。
バナナは胃腸に負担をかけにくいため、もちろん試合前のエネルギー補給にも適しており、消化吸収される時間から逆算して運動前1時間くらいまでに食べるとよいとされています。
ただし、運動前1時間を切った場合、固形物は消化が間に合わないため、エネルギー補給専用のドリンクやサプリメントを利用するのがおすすめです。
また、バナナは炭水化物も豊富にあるため腹持ちもよく、長時間の運動にも最適なエネルギーになります。
学校や仕事終わりの夕方に、クラブ活動やスポーツジムに行く方、残業がある方にも間食として適しているといえるでしょう。

食事や間食の代わりに
人は、ビタミンB1が不足すると、糖質からエネルギーをつくることができず、だるさや疲労、食欲不振といった症状が表れます。
バナナには、糖質をエネルギーに変換するビタミンB1が含まれています。
お昼の休憩にいく時間がない、午後も集中したい、長時間の作業になりそう、という時には、糖質とビタミンB1が含まれるバナナを食べるとよいでしょう。
バナナは、タンパク質や脂質が含まれていなく、皮をむくだけでさっと食べられるため、忙しい時や小腹が空いた時にも手軽に食べられます。
間食やおやつは、お菓子やパンなどを食べるよりも、1本程度のバナナなら毎日食べてもリスクはなく腹持ちもよいです。
また、食事をバナナだけにすると、1食あたりのカロリー摂取量を減らすことにもつながるため、ダイエット効果が期待できます。
ちなみにバナナのカロリーは、日本食品標準成分表によると100gで約86kcalです。
バナナ1本のカロリーでいうと、皮を除いた可食部100gで93kcalあり、ご飯1杯(150g)の234kcalや食パン1枚(80g)の197kcalより、かなり低い値といえます。
バナナの効果的な保管方法・体験
暑い地域で育つバナナは低温に弱く、冷蔵庫に入れると追熟が進まず、低温障害で皮が黒く見た目も悪くなります。
バナナを長持ちさせたい時は、常温で好みの状態に追熟させてから、新聞紙やペーパータオルなど湿気を吸収しやすい紙に包んでビニール袋に入れ、冷蔵庫の野菜室に保存するのが最適です。
日持ちさせたいからといって、購入後すぐにバナナを冷蔵してしまうと、食感が硬くなり、甘味が足りない状態になってしまいます。
筆者は、冷蔵庫で冷やしたバナナを食べると、胃に負担がかかるのか、固形物が留まったような違和感があり調子が悪くなります。
バナナを冷やすと栄養価が下がるのか、成分が固まって効果を出せなくなるのかと思ったのですが、調べてみるとある可能性が浮かびました。
バナナは、熱帯性植物であるため冷気に弱く、13℃以下の冷蔵庫に入れると皮の細胞が壊れてしまい、熟成が止まってしまいます。
バナナだけとは限りませんが、果物や野菜は熟成することによって栄養価が上がっていきます。
そのため、追熟が進んでいないまま冷蔵庫に入れて冷やしてしまうと、成熟が止まってしまい、それ以上栄養価が上がらなくなってしまうのです。
つまり、バナナを購入したらすぐに冷蔵庫に入れるのではなく、数日ほど常温で好みの状態に追熟させてから冷蔵庫に入れるのが適しています。
なお、冷蔵庫に入れる前より栄養価が落ちるということではないため、冷蔵庫で保存すること自体は問題ありません。
とはいえ、冷たいバナナは果肉が硬く、甘味を感じないため、筆者はバナナを購入したら冷蔵庫に入れず、常温に近い状態で保存し食べています。

追熟とは
追熟(ついじゅく)とは、一部の果物などを収穫した後に一定期間置くことで、甘さを増したり果肉をやわらかくする処理のことをいいます。
バナナの変色について
バナナは収穫後でも呼吸をしていて、バナナに含まれるポリフェノールが酸化をすることで皮が茶色に変化します。
運搬中の加圧や保存する時に傷が入ってしまったことにより、ポリフェノールの酸化が早まることもあります。
機能性表示食品のバナナとは
さまざまな種類が揃うバナナですが、例えば血圧が高めの方には「機能性表示食品」のバナナがよいといわれています。
販売する企業サイトによると、高めの血圧を低下させる機能が報告されているGABA(γ-アミノ酪酸)を含んだバナナは、機能性表示食品として消費者庁が認めた食品です。
GABAとは
GABA(ギャバ)は、γ-アミノ酪酸というアミノ酸の一種で、バナナに多く含まれる旨味成分のグルタミン酸が、実の成長とともに変化してできる自然由来の成分です。
このGABAが、血圧上昇の原因となるノルアドレナリンの発生を抑え、血圧が上がりすぎるのを防ぎます。
GABAに期待される効果としては血圧を低下させるだけでなく、気分を落ち着かせたり食べ過ぎを防いだり、他にもストレス軽減や認知機能の改善、良質な睡眠などがあります。
機能性表示食品とは
機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品です。
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。
ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
出典:消費者庁サイト
※疾病の診断や治療、予防を目的としたものではありませんのでご留意ください。
※食品を買う前や摂取する前に、商品パッケージに表示されている注意書きや消費者庁のWebサイトに公開された情報を確認してください。

次項では、筆者が市販のバナナを食べてみた感想と効果を紹介します。
なお、あくまで個人的観点であり、個々の体質によっても感度や効果が異なるため、バナナ選びの参考になれば幸いです。
極撰バナナ(Dole)
Doleが販売する極撰バナナは、GABAパッケージとレジスタントスターチパッケージの2種類あります。
同じ「極撰」という表記で間違えそうになるため、パッケージの記載内容に注意してください。
GABAの極撰バナナ
Doleのサイトによると、GABAパッケージの極撰バナナは、フィリピンの標高500m以上の高地栽培で、通常のバナナが約10ヶ月で収穫できるのに対し、1年以上とより長い期間をかけて収穫されます。
昼夜の寒暖差が大きい高地で栽培すると、糖分に変換されるデンプン質が増えて、甘いバナナに育つとのことです。
また、同バナナは、GABAを6.2mgも含んでいる機能性表示食品として登録されています。
レジスタントスターチの極撰バナナ
レジスタントスターチパッケージの極撰バナナは、Doleが研究・開発した100種類以上の中から選び抜いた、高地栽培バナナです。
食物繊維と同じように、腸内環境を整える効果が期待されるレジスタントスターチを含んだバナナのため、機能性表示食品ではありません。
完全な黄色で熟している状態のバナナ「フルイエロー」のバナナに比べると、両端に緑色が残っている「グリーンチップバナナ」の方がレジスタントスターチが多く含まれており、その量は約1.25倍とのことです(2022年7月時点、ドール調べ)。

極撰バナナを食べた感想・効果
筆者は高血圧でもないのですが、他の効果面でDoleのバナナは、他のバナナより優れていることを実感できており、「極撰」と書かれているパッケージのバナナを毎朝摂っています。
極撰バナナは、他のバナナに比べると値段が比較的高価ですが、多くの収穫したバナナから極上の品質を選び抜いた手間を考えると納得ができるほど、もっちりとした噛み応えと濃い甘さがあります。
そして、他のバナナよりも消化吸収が早いため、排便の量も多くなり、切れがよいため調子がいいです。
ただ果肉がしっかりしている割に、皮が比較的薄いため変色が早く、衝撃にも弱いからか縦に割れ目が入ることがよくあるため、見た目に神経質な方には向かないかもしれません。
スウィーティオバナナ
Doleが販売するスウィーティオバナナも、前述の極撰バナナと同じく、GABAパッケージとレジスタントスターチパッケージの2種類あります。
スウィーティオバナナにおけるGABAパッケージと、レジスタントスターチパッケージの特徴は、極撰バナナと変わりませんが、じっくり育成させ収穫した後は、日本国内で味覚調査を行い、日本人の嗜好に合わせて甘さとコクを追求したものだそうです。
スウィーティオバナナを食べた感想・効果
スウィーティオバナナは、極撰バナナより値段が安いですが、甘みが少なめで歯応えに物足りなさを感じたため、極撰バナナの方を購入しています。
極撰バナナは、スウィーティオバナナと同じ標高500m以上の高地栽培ですが、Doleが100種類以上あるバナナの品種から、糖度やサイズ、香りなどを基準に選定を行い、わずか1~2%しか選ばれないというエリート中のエリートバナナであるそうです。
もちもちとした食感と強い甘みを考えると、料金設定とともに頷ける品質だと感じています。
甘熟王バナナ(スミフルジャパン)
甘熟王バナナも、機能性表示食品として登録されており、販売元であるスミフルジャパンのサイトによると、フィリピンのミンダナオ島アポ山系など、標高700m前後の高地で栽培された食品です。
朝と夜の気温差が大きいため、育成期間が通常のバナナで約10ヶ月に対し、甘熟王バナナは約14ヶ月前後と長いため、多くのデンプン質が蓄えられるとされています。
人は、GABA(γ-アミノ酪酸)を20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる作用があります。
甘熟王バナナには、GABAが1本当たり10mgを含んでおり、可食部120g(1~2本)を食べると、1日あたりの機能性関与成分量の50%を摂取できることになります。

甘熟王バナナを食べた感想
筆者が、甘熟王バナナを食べた感想としては、皮は程よく厚みがあり、極撰バナナのように縦に割れ目ができることはありません。
果肉は少し空気を含んでいるほど柔らかく、すっきりした甘さです。
また、もっちりとはしていませんが、粘りがなく歯切れがよい感触があり、他のバナナよりも皮に厚みがあるせいか、変色しにくいイメージがあります。
極撰バナナよりは少し劣るものの、排便の調子はいいです。
他の市販バナナについて
スーパーなどでよく見られる他の市販バナナも食べてみました。
デルモンテ・バナナ
デルモンテのバナナは、スーパーで他のバナナより大量に積み上がっている定番のバナナです。
当初は、98円の時もあったほど値段が安くて、1コーナーにあふれるほどたくさん積んでいるのをよく見かけます。
他のバナナよりも数で目立つ、このデルモンテのバナナを以前は毎週購入していましたが、一時買えなかった時期があり、傍にあった甘熟王バナナを購入してみたところ、味や歯応えが全く違い、以後は買わなくなってしまいました。
デルモンテ・バナナは、糖分を必要以上に感じないヘルシーさで、さっぱりとした甘さが特徴です。
ただ、シンプルさがいいものの満腹感をあまり感じないため、朝に食べても昼過ぎまでエネルギーがもたない印象がありました。

田辺農園のこだわりバナナ
田辺農園のこだわりバナナは、日本人の田邊正裕さんが現地で栽培するエクアドル産のバナナです。
農園は畑ではなく、可能な限り自然に近い、まるで森のような環境を保ち、土と水にこだわった自然循環型農法により栽培されています。
一般的なバナナに比べて多少値は張りますが、甘くしっかりした濃厚な味で食べやすいです。
インカバナナ
インカバナナは、松孝が販売するペルー産の有機栽培バナナです。
雨季に河川が氾濫することで運ばれてくるアンデス山脈の土壌で育ち、グアノという海鳥の糞を肥料にしているため、化学肥料は使っていないそうです。
果肉は柔らかめで、まろやかな甘みとほんのり酸味があります。

じんわり熟成おいしいバナナ
じんわり熟成おいしいバナナは、松孝が販売するエクアドル産のバナナです。
もっちりとした程よい柔らかさで、酸味はほとんどなく甘味はしっかり感じられます。

終わりに
私たち人間の脳は、ブドウ糖をエネルギー源としています。
ただし、ブドウ糖は体内に多く蓄えておくことができないため、毎食糖質を摂ることが必要です。
バナナは、ブドウ糖をはじめとするさまざまな糖質が多く含まれており、寝ている間に失われたブドウ糖を補うのにも適しています。
仕事や勉強、運動に集中するためにも、朝食や直前にバナナを摂ることで脳のエネルギーを補充しておきたいものです。
また、バナナに含まれる食物繊維は、オリゴ糖と一緒に腸内環境を整え、マグネシウムは腸の動きを活発にし、便通を促す働きがあります。
バナナで心身ともにすっきりした状態で、1日を快適に過ごしましょう。

以下の記事では、同じブドウ糖で天然栄養成分の宝庫ともいわれるハチミツについて紹介しています。
古くから生薬としても重宝されてきたハチミツの種類や違いから、栄養成分とそれぞれの作用、効果的な食べ方・注意点を解説していますので、併せてご参考ください。
-

-
ハチミツの驚くべき栄養成分とその効能とは?効果的な食べ方や相性のいい食材5選
2024/3/29